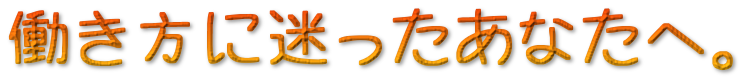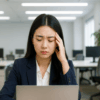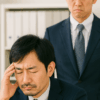【飲み会は行くべき?】~断ることで評価が下がる不安との向き合い方
無理してまで参加する必要はない

・「仕事終わりの飲み会に誘われるたび、断ったら評価が下がるのでは…と不安になる」
・「お酒が苦手なのに、無理して参加してしまう」
・「一次会だけで帰りたいのに、空気を読んでつい二次会へ…」
・「飲み会に行かない自分は、協調性がないと思われてしまうのでは?」
実は、こうした悩みを抱える20代の会社員は少なくありません。
本来、飲み会はコミュニケーションを深める場のはず。
しかし、「行く・行かない」が評価や、
職場の人間関係に直結すると感じるからこそ、多くの若手社員は葛藤しています。
背景には、
・"飲みニケーション"を重視する古い職場文化
・企業での“参加が当然”という同調圧力
・SNSやネットでも「飲み会に行かないと出世できない」という古い情報が広がっている
など、こういった要因があります。
つまり、断ることそのものよりも、
**「断った結果どう思われるか」**という不安が大きな問題なのです。
ただでさえ、職場の雰囲気に馴染めないミキは、会社で飲み会があるたびに参加したくないというのがホンネのようです。。

「正直、飲み会ってあまり得意じゃないんです…。
お酒も弱いし、気を使ってばかりで、全然リラックスできなくて。。
でも、誘われるたびに断ると、“ノリが悪い”とか“生意気”って思われるんじゃないかって不安になるんです。
周りの目を気にして、結局いつも参加してしまうんですよね。
一次会で帰りたいなって思っても、“もう帰るの?”って言われるのが怖くて…。
断り方一つ間違えるだけで、翌日気まずくなるんじゃないかって考えちゃう。。
本当は、仕事が終わったら早く家に帰って休みたいだけなんですけどね…。
それすら“わがまま”に見える職場の空気がツラいです。」
私自身も20代の頃、
営業職で頻繁に飲み会に誘われたり、
自衛隊に入ってからは、『飲み会は毎回、参加必須』な"飲み文化"を経験してきました。
当時はそういった文化を受け入れていましたが、
今思えば、“先輩たちからの無言の圧力に逆らえなかった"だけでした。
一方で、今時の20代の若者の中には、割ときっぱり、態度を鮮明にしている人もいますね。
『参加する利点がなければ行きません。』みたいな。
積極的に参加する人。
明確な理由がない限り、参加しない人。
これまでに数多くの事例を見、実際に双方の立場の人たちと議論を繰り返してきました。
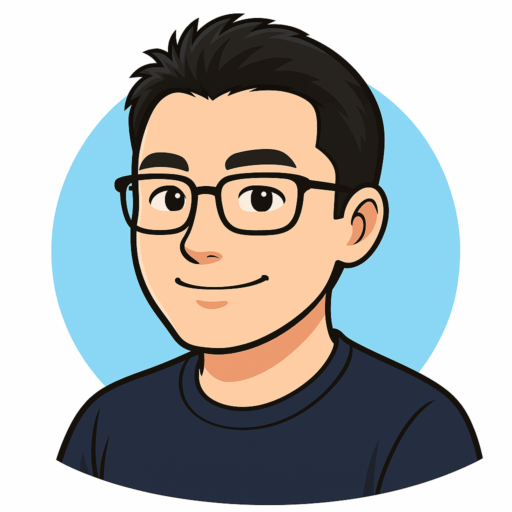
本業は会社員の40代ブロガー。
これまでに自衛隊や複数の民間企業など、
通算7度の転職を経験し、数多くの人間関係に悩み抜き、
そこから多くの教訓を学ぶ。
2019年から副業としてブログを始め、複数の特化ブログを運営。
2025年からは当ブログ『働き方に迷ったあなたへ。』をスタート。
働き方の多様性やその価値観について継続発信中。
この記事では、「飲み会に行かない不安」との向き合い方を整理し、
・飲み会に行くべきか迷ったときの判断基準
・職場での評価を下げずに断るための具体的なコツ
・飲み会以外で信頼を築く方法
などについて解説していきます。
この記事を読むことで、
・「飲み会に行かないと評価が下がるかも…」という不安から解放され、
・自分に合った参加スタンスを選べるようになり、
・仕事とプライベートのバランスを守りつつ、信頼関係を築けるようになります。
飲み会は「行くか・行かないか」で評価が決まるものではありません。
大切なのは、自分のスタンスを保ちつつ、普段の仕事と人間関係で信頼を積み重ねること。
無理に職場の雰囲気に合わせる必要はなく、
あなた自身の働き方に合った付き合い方を選んでいけばいいのです。
20代会社員が抱える「飲み会」の不安とは。。
断ったら評価が下がるのでは?というプレッシャー

多くの20代が抱えるのは、
「飲み会に行かないと、やる気がないと思われるのでは」という不安です。
特に入社間もない時期は「協調性を見られている」と感じやすく、
ミキのように、つい無理をして参加してしまうケースも少なくありません。
また、職場の先輩社員も、単純に『若手ともっと交流して理解し合いたい』とか、
『理解し合うことで仕事をやりやすくしたい』と考えて誘っているケースもあり、
これがかえって若手社員のプレッシャーを増幅させている向きもあります。
お金・時間・体力の負担が大きい

飲み会は1回で数千円が飛んでいきます💸
月に何度も重なると大きな出費になり、
終電までの時間調整や、翌日の仕事に響くこともあり得ます。
そのため、『わざわざ時間や体力を削ってまで参加する意味があるのか?』と、
疑問を抱く人も増えているわけです。
お酒が苦手でも断りづらい空気
「お酒が飲めないけど、周りの視線が気になる」
「場をしらけさせるのでは。。」
といった心理的ハードルもあります。
断りにくい雰囲気は、若手にとって大きなストレスです。
『協調性がないと思われる』ことへのメンタルダメージは意外なほど大きいのです。
飲み会は本当に「行かないと損」なのか?
昔ながらの“飲みニケーション文化”の背景
高度経済成長期から続く「飲み会=上司と部下の距離を縮める場」という文化は、今も根強く残っています。
かつては人事評価や出世に直結するとも考えられてきました。
信じられないかもしれませんが、
「あいつは付き合いが悪い」みたいな理由で、
昇進が遅れてしまう会社も珍しくありませんでした😱
実際に評価へ影響するケースとしないケース

確かに一部の職場では、飲み会での振る舞いが「協調性」や「人柄」として評価対象になることもあります。
一方で成果主義やリモートワークが浸透している今の時代では、
飲み会に参加するかどうかはほとんど影響しないと言っていいでしょう。
成果主義の職場では飲み会の影響は小さい
実際、多くの人事担当者は「評価は仕事の成果や日頃の勤務態度などで決まる」と語っています。
つまり、無理して飲み会に出なくても、普段の行動で信頼は十分築けるのです✨
飲み会を断っても評価が下がらないためのポイント
ここでは、あなた自身が後日、
職場で不利益を被らないような断り方について解説していきます。
「なんでそんな、断り方までいちいち、、」と思うかもしれませんが、
相手の気持ちを考えつつ、こちらの意思を示すのも、
立派なコミュニケーションスキルの一つです。
断り方が9割!「感謝+納得できる理由」を伝える

ただ無愛想に「行きません」と突っぱねるのではなく、
**「お誘いいただいてありがとうございます。ただ明日は朝から大事な用事がありまして…」**と、
感謝と理由をセットにすると、だいぶ印象が変わります。
これには、日頃からのコミュニケーションも大きく影響してきます。
ふだんから職場の上司や同僚と雑談を交わしているような仲であれば、
よほどのことがない限り、
明確な理由を述べている仲間に対してムリに参加をすすめてくることはないでしょう。
全て断らず「一次会だけ・2回に1回」などバランスを取る
「絶対に行きません!」という姿勢ではなく、
参加と欠席をうまく組み合わせるのも現実的ですし、そこまで角が立ちません。
たとえば一次会だけ顔を出す、隔回で参加するなど、
柔軟なスタンスをとることによって、あなた自身の負担もやわらぎ、
職場の同僚にも必要以上に違和感を抱かれなくなるでしょう。
普段の仕事やコミュニケーションで信頼を築く
飲み会に出ない分、日常の業務で誠実に取り組むことや、
挨拶やランチでの会話などを大切にすることで、信頼を補うことができます。
ふだんから仕事で信頼を得ている同僚に対しては、
職場のメンバーも『あいつは仕事できるからな。まあ、参加しなくても。』となりがちです。
断りづらいときに使える具体的フレーズ集
『実際、断るにしても、周囲の同僚が納得するような理由が浮かばない。』なんてこともあるでしょう。
ここでは、そういった方のために役立つフレーズを以下にまとめて紹介します。
体調・翌日の予定などを理由にする場合
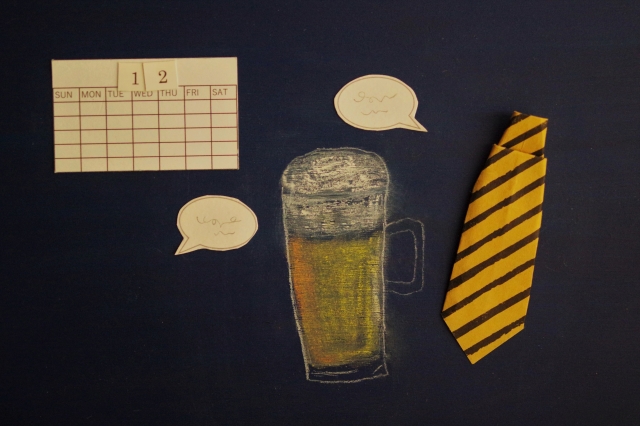
「明日の朝からプレゼンがあって、今夜はその準備に集中したくて…」
など、仕事が理由であれば、それを妨害してまで参加しろと言ってくる人はいません。
あるいは、
「最近体調を崩しがちなので、今日は休ませてください」
など、体調不良を訴えれば、仮に参加を無理強いされても、
最悪、途中でそれを理由に離席・帰宅することもできます。
金銭的・家庭的な事情を理由にする場合

「今月ちょっと出費が重なっていて…」
「家族との予定があるので、今日は失礼します」
最近は物価高の家計に対する影響もあり、
こういった理由で断ることも珍しくなくなりました。
また、妻(夫)や息子・娘の誕生日など、
家族で過ごすイベントに対する会社の理解も以前に比べれば進んでいるように思います。
会社によっては、『誕生日休暇』を設けているところもあるくらいで、
該当社員に対しては飲み会への参加を促すことなど、まずないでしょう。
ポジティブに断る「また誘ってください」の一言
それぞれ明確な、納得し得る理由を述べるのも良いですが、
断った後に「次回またぜひお願いします」などと添えると、
単なる拒絶ではなく、前向きな印象を残せます。
また、職場の同僚に信頼感を残すためにも、
なるべく参加できる時は飲み会に顔を出し、
一次会だけでも付き合うようにすれば、いざという時に断りやすくなります。
飲み会以外で人間関係を深める方法
「飲み会に参加しなければ人間関係を構築できない」なんてことはありません。
それ以外の場でも十分に関係を築く方法を紹介します。
ランチや休憩時間の小さなコミュニケーション

短時間でも「一緒にランチ」「ちょっと雑談」ができれば十分に距離を縮められます。
休憩時間は一時、仕事から離れることのできる時間。
なかには休憩時間にも仕事の話をしてくる先輩もいるでしょうし、
多忙な時には、そうならざるを得ない場合もあるでしょう。
ですが、仕事であれ、それ以外の雑談であれ、
ある程度まとまった時間、会話するわけですから、
互いの人間性を知り合う良いきっかけとなります。
仕事のサポートや成果で信頼を積み重ねる

残業を手伝う、資料を共有するなど、日常のちょっとした助け合いが信頼につながり、
良い人間関係を築くことになります。
若手のうちは手伝うことのできる範囲も限られるかもしれませんが、
『これなら自分にもできそう』という場面があれば、
積極的に『手伝います』と、声をかけてみましょう。
もちろん、ふだんから気を遣いすぎてもかえってストレスが溜まりますので、無理のない範囲で。
オンライン交流・趣味の共有で距離を縮める
最近はチャットツールなどオンラインでの交流、
または趣味の話題をきっかけに関係を築くケースも増えています。
職場の上司や先輩とプライベートな時間にまで関係を持ちたくない方がほとんどだと思いますが、
ご自身が夢中になっているものに関して、
上司や先輩がむちゃくちゃ詳しかったとしたらどうでしょうか?
意気投合し、場合によっては仕事のことも忘れて話してしまうかもしれませんね。
そうそうないかもしれませんが、"趣味仲間"と呼べるくらいの関係になれば、
職場の飲み会などに参加せず、プライベートで飲みに行ったりする機会も出てくるでしょう。
無理に参加しなくても大丈夫!自分に合った選択を
飲み会に行かない選択を肯定する時代へ

「飲み会=絶対参加」という考え方は過去のものになりつつあります。
生き方・働き方の多様性が進んでいるくらいですから、
今の20代の方々には到底理解し得ないものでしょう。
逆に、そういった若手の価値観やライフスタイルを尊重する職場も増えています。
現在の私の職場でも、いわゆるZ世代の若者は『いや、参加しませんね。』と、
何も気にすることなく堂々と発言してます。
もともと"参加の自由"を尊重している職場ですから、
『行きませんか?』と誘うことはあっても、
『できれば参加した方がいいですよ。』などと促すことすらしません。
このように、今の世相を反映した職場も少しずつ増えているのです。
ハラスメントに感じたらどうすべきか

繰り返しの強要や「来ないと出世できない」といった発言は、
アルハラ(アルコールハラスメント)やパワハラに該当する可能性があります。
あまりに誘い方が露骨でひどい場合には、
職場の相談窓口や外部機関を利用することも視野に入れましょう。
自分の働き方を大切にすることが最優先

職場での評価を気にして無理に参加するよりも、
プライベート、自分の時間を優先した方がはるかに有益です。
ここまでで述べてきたように、
飲み会以外の場でも人間関係を築くことは十分できますので、
仕事以外の時間をムダにしないようにしましょう。
飲み会に参加して飲み代を払うくらいなら、
そのお金で書籍を購入する方がご自身の将来にとって役立つでしょう。
たまに参加して職場の仲間とワイワイ気分転換をするのであれば良いでしょうが、
気の進まない飲み会に無理してまで参加する必要はありません🖐️
まとめ:飲み会は「評価のため」ではなく「自分のため」に選ぶ

ここまでの記事内容をまとめます。
・飲み会に行くかどうかで評価が決まるわけではない
・大切なのは断り方と、普段の仕事での信頼構築
・無理に合わせず、自分に合ったスタイルを選んでよい
飲み会は「評価を守るための義務」ではなく、
あくまでも『職場の同僚とどう関係を構築していくか』を考えるうえでの選択肢の一つに過ぎません。
あなた自身の働き方や価値観を大切にしながら、
無理のない範囲で関係を築いていけば良いのです。
この記事で紹介した考え方、断り方などを参考に、
飲み会との適切な距離をとっていきましょう。
今後、周囲の視線を気にしたり、職場に気を遣ったりする必要はありません。
あなたらしく振る舞っていきましょう!
当ブログでは、他にも『人間関係に関する悩み』について多くの記事を掲載しています。
今、あなたが抱えている悩みを解きほぐす記事もあるかもしれません。
よければ参考にしてください👇😀