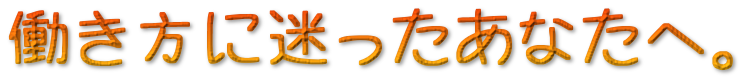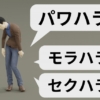【求人に“年齢制限あり”は本当にダメ?】40代の求職者目線で読み解く企業の意図と対処法
転職に“年齢制限”は本当にあるのか?40代が知っておくべき現実と対処法

「年齢だけが理由でチャンスを逃したくない。。」
そう感じていませんか?
・求人票に「35歳以下」「40歳まで」と書かれていて応募をためらう
・「40代でも転職できるのかな…」と不安に感じる
・面接で年齢を理由に落とされた経験がある
・「もう若くない」と諦めてしまいそうになる
45歳のコウジも、現在、まさに同じ悩みを抱えています。
転職サイトで見かけた「年齢制限あり」の文字に、心がざわつく――。
でも、それって本当に“応募してはいけない”求人なのでしょうか?

「“35歳まで”って書かれてるけど、
これって本当にアウトなのかな…。
経験やスキルがあれば、そんなの関係ないような気がするけど、、
ただ年齢だけでチャンスを閉ざされるのは、なんか納得いかない。」
実は、現在の日本では”原則として”年齢制限を設けた求人はNGです。
それにもかかわらず、現実には“暗黙の年齢ライン”が残っており、
多くの40代・50代が「書類すら通らない」という壁にぶつかっています。
この“年齢制限の名残”を正しく理解せずに転職活動を進めると、
せっかくのチャンスを自ら逃してしまうリスクもあります。
つまり、「年齢制限=応募不可」と短絡的に判断してしまうのは、
転職を成功させるうえで、非常にもったいないことなのです。
私はこれまでに7回の転職経験を重ねてきましたが、
そのほとんどが40代以降の転職であり、
それこそ転職市場の“年齢の壁”を何度も体感してきました。
その過程で感じたのは――年齢が問題なのではなく、
「企業が何を求め、それに対して自分がどう伝えるか」を理解できていないことでした。
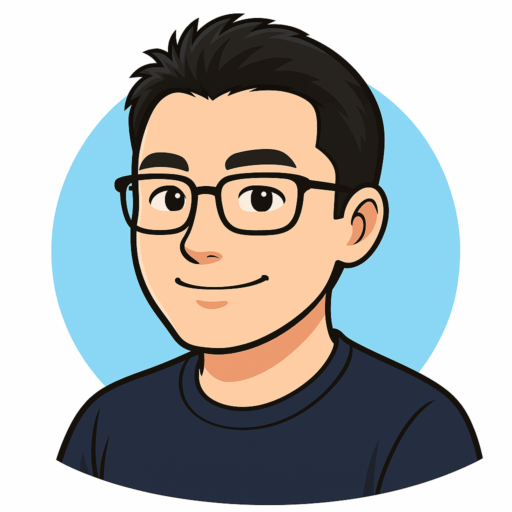
本業は会社員の40代ブロガー。
これまでに自衛隊や複数の民間企業など、
通算7度の転職を経験し、「人間関係の悩み」など数多くの教訓を学ぶ。
2019年から副業としてブログを始め、
「転職」や「働き方」に関する記事を継続発信中。
この記事では、「求人に年齢制限があるのは本当に違法なのか?」という法律面の基礎から、
40代以降の求職者が“年齢制限あり求人”とどう向き合うべきか、
そして“年齢の壁”を突破するための戦略までを、求職者の目線で丁寧に解説します。
この記事を読むことで、
・「年齢制限あり=応募NG」という思い込みを手放せる
・企業が年齢を気にする“本当の理由”を理解できる
・40代以降でも採用される人の考え方と戦略がわかる
というメリットを得られます。
つまり、“年齢”という不安を武器に変えるヒントが得られるのです。
転職で大切なのは、年齢ではなく「あなたが何を提供できるか」。
『年齢制限』という言葉に縛られず、
”自分の経験をどう活かすか”を考えることが、成功への第一歩です。
求人の年齢制限は本当に違法?|禁止の背景と例外条件を知ろう

「40歳以下」「35歳まで」──
求人票にこうした年齢条件を見かけると、思わず応募をためらってしまいますよね。。
「年齢制限って、そもそもアリなの?」と感じる人も多いでしょう。
実は、日本では**原則として求人における年齢制限は“禁止”**されています。
これは、2007年に施行された「労働施策総合推進法(旧:雇用対策法)」によって明確化されたルールです。
つまり、企業は年齢を理由に応募者を排除してはいけない、というのが基本方針になっています。
しかし、実際の転職市場を見渡すと、まだ“暗黙の年齢ライン”が存在しています。
この矛盾の背景には、法律だけでは解決しきれない「企業側の事情」もあるようです。
なぜ年齢制限は設けられなくなったのか?(労働施策総合推進法の影響)

2000年代に入ると、少子高齢化が急速に進み、
「年齢を理由にチャンスが奪われる社会構造」を是正する流れが強まりました。
そこで政府は2007年、「労働施策総合推進法(旧・雇用対策法)」を改正し、
企業に対して次のような義務を課しています。
✅ 原則として、求人・採用において年齢制限を設けてはならない。
✅ もし設定する場合は、“合理的な理由”が必要。
たとえば、「35歳まで」と区切ってしまうと、
それ以上の年齢の人材が能力を発揮する機会を奪うことになり、
労働市場全体の活力を下げてしまう恐れがあります。
この法改正は、単なる形式的なルールではなく、
“すべての人に働くチャンスを”という社会的メッセージでもあります。
しかし――実際に求人を見ていくと、現場ではまだ完全には浸透していない現実があります。
私自身、40代になってからの転職を5社ほど経験してきましたが、
まず「書類選考が通らない」という事実を何度も何度も突きつけられ、
そのたびに、「これ、やっぱり年齢が原因だよね。。」と、かなり諦めモードになっていました。
ですから、コウジのように、40代半ばで転職活動に苦しむ方々の気持ちは痛いほど分かります。
それでも一部で年齢制限が残るケースとは?

「法律が改正されたんだったら、、今でも“年齢制限あり”と書かれている求人は違法なの?」
と問いたくなりますよね?
――答えは「必ずしもそうとは限りません」。
法律上、企業が年齢制限を設けられる“例外”がいくつか定められています。
代表的なものを挙げると、次の通りです。
| 例外が認められるケース | 具体例 |
| 定年年齢を上限とする場合 | 定年60歳の企業で「60歳未満の方」など |
| 長期キャリア形成を目的とする場合 | 若年層の育成を目的とした「35歳以下」など |
| 特定の業務で安全上の配慮が必要な場合 | 警備・消防・運転業務など |
| 芸能・モデルなど、表現に年齢条件が不可欠な場合 | 役柄上、年齢指定が必要なケースなど |
こうしたケースは、“合理的な理由”がある場合に限って認められます。
つまり、すべての「年齢制限あり求人」が違法というわけではなく、
あくまで“例外的に”容認されているものなのです。
ただし、ここに盲点があります。
法律上の建前としては「禁止」が原則でも、
現場レベルでは「採用側の意図」が求人票に表れにくいという点です。
これは私自身の体験からもはっきりと言えます。
求人票には「年齢不問」とありながらも、実際に面接の場に臨んでみると、
『うちは血気盛んな20代・30代が比較的多いですよ。その中で、一緒に頑張っていけるだけの熱意を持てますか?』
と、半ば、”あなたには無理じゃないの?”という意図を匂わせていたパターン。
だったら、最初から求人票にそう記載してくれよ、と言いたくなっちゃいますよね。。。
つまり、表面上は“年齢制限なし”でも、実質的に存在しているケースが少なくありません。
そのため求職者は、「表記」ではなく、常に「企業の意図」を読み取る視点が欠かせないと言えるでしょう。
この章では、年齢制限の「法的な建前」と「現場の本音」を理解することが重要です。
次章では、40代以降の求職者が「年齢制限あり求人」に応募すべきか――。
その“リアルな判断基準”を見ていきましょう。
40代以降の求職者が「年齢制限あり求人」に応募するのはアリ?

「年齢制限あり」と明記された求人を見ると、
つい、「自分は対象外なんだな…」と感じてしまいますよね。
『長期キャリア形成のため、35歳まで』とか、
私もそういった求人を見つけるたび、最初はそう思って応募をやめていました。
しかし、ある時ふと気づいたのです。
「本当に年齢だけで判断していいのか?」
実は、“年齢制限あり求人”の中にも、
40代以降がチャンスをつかむ可能性は十分あります。
ポイントは、その**“裏にある企業の意図”を読み取ること**です。
「年齢制限あり求人」は“本気度の高い転職者”が見極めるべきサイン

企業が年齢制限を設けている場合、
それは「どんな人材を求めているか」を示す“サイン”でもあります。
たとえば「35歳以下」「40歳未満」と書かれている求人。
一見「若手限定」に見えますが、実際には次のような意図を持つケースがあります。
・若手を採用したいが、柔軟に育成できる人材を求めている
・組織の年齢バランスを整えたい
・中長期的にマネジメント候補を育てたい
つまり「今の40代は対象外」ではなく、
「これからの組織づくりを考えた採用方針」なのです。
ここで大事なのは、
「年齢制限がある=応募NG」ではなく、
“自分の経験やスキルがその意図にマッチしているか”を見極める姿勢なのです。
私は、そう考えるようになってから、
「年齢制限あり求人」も“企業が与えてくれた情報のヒント”として冷静に見るようになりました。
結果、応募先の選択肢がぐっと広がったのです。
年齢で不採用になるケースは?実際の企業心理を読み解く

もちろん、年齢がネックになるケースもあります。
ただしその理由は、単純に「年を取っているから」ではありません。
企業が年齢を気にする背景には、以下のような“心理”が隠れているわけです。
| 企業側の本音 | 背景 |
| 教育・育成コストを抑えたい | 経験者採用が前提で、即戦力を期待している |
| 組織の年齢バランスを取りたい | 上司より年上だとマネジメントが難しいケースも |
| 将来的な給与バランスを考慮している | 同年代社員との待遇差を避けたい |
| 「転職回数が多い」「指導を受けにくい」などの先入観 | 過去の人事経験からの思い込みも |
つまり、年齢そのものよりも、
**「採用後にどんなリスクがあるか」**を企業は気にしているのです。
この視点を理解できれば、面接での伝え方も変わります。
「年齢が高い=柔軟性がない」と思われがちな点を、
「経験を活かして若手を支える立場になれる」と逆手に取ることで、印象を好転させられます。
私自身、このように企業側の隠れたホンネに気づくようになってから、
「年齢の壁」が少しずつ薄れていく実感を持ち始めました。
そりゃ、そうですよね。
20〜30代の若手が中心の職場に40代のオッサンが入っていったら、
何か教えるにしても扱いにくいだろうし、煙たがられるのは自然なことでしょう。
企業側のそういった”心理的バリア”を解きほぐすには、
自分がいかに謙虚で知識欲旺盛か、などなど、こちらの伝え方にもよると考えたのです。
年齢を超えて採用される人の共通点とは

実際に40代・50代で採用を勝ち取る人には、いくつかの共通点があります。
① 自分の市場価値を正しく理解している
→「何ができるのか」「どんな成果を出してきたか」を数字で示せる。
② 柔軟に学ぶ姿勢を持っている
→「今後の成長に意欲がある人」は、年齢に関係なく評価される。
③ 組織に溶け込むコミュニケーション力がある
→「協調性」「素直さ」「謙虚さ」は年齢よりも重要。
特に注目すべきは、「経験の深さ」よりも「活かし方」にあります。
過去の実績を“誇る”のではなく、“現場でどう役立てられるか”を語れる人が強いです。
“ベテラン感”を出すより、“一緒に成長できる人”であることを見せた方が、
協調性があることをアピールできますし、十分、評価の対象になり得ます。
企業が年齢を超えて採用を決めるのは、
スキルやキャリアの差よりも、その人の姿勢と考え方なのです。
次章では、
「年齢制限を気にせず応募すべき求人」「避けるべき求人」の見分け方を、
具体的に解説していきます。
年齢制限を気にせず応募すべき求人・避けるべき求人の見分け方

求人を見ていると、
「年齢制限なし」と書かれていても、ホンネでは若手を採りたい企業もあります。
逆に「経験重視」など、実は40代以上が歓迎されるケースも少なくありません。
では、そういった求人票をどうやって見分ければいいのでしょうか?
ここでは、“求人票の言葉選び”に隠された企業の本音を読み取る方法を紹介します。
私自身、転職を繰り返していく中で、最初はただ求人内容だけを見ていました。
しかしあるとき気づいたのです。
「同じ“未経験歓迎”でも、会社によって意味が全然違う。」と。
ポイントは、“求人の書き方”そのものにあります。
「年齢より経験重視」と明記している求人はチャンス

まず注目すべきキーワードは、「年齢より経験重視」、「人物重視」、「即戦力歓迎」などです。
これらのフレーズは、文字通り、採用時に年齢よりスキルや実績を優先する姿勢を示しています。
特に40代以降の転職者にとっては、こうした求人が“勝負どころ”です。
企業は次のような意図を持っていることが多いものです。
・チーム全体を支える中核人材を探している
・即戦力として早期に成果を出せる人材を求めている
・業界経験者を優先しつつ、安定して長く働ける人を評価している
つまり、「年齢よりも、これまで何をしてきたか」が重視されるということ。
これこそ、40代の人材がこれまで積み上げてきた経験やコミュニケーション力などを発揮すべき場です。
私は、とある転職面接の場において、長年の自衛隊勤務で培ってきたマネジメント経験や部下とのコミュニケーションの取り方などを具体的に話したところ、かなり良好な評価をいただくことができました。
「“あ、この人なら任せられる”」と、面接官の表情が変わったのを覚えています。
求人票で“経験重視”と書かれている場合、
年齢のハードルは想像以上に低いケースが多いのです。
むしろ、40代ならではの落ち着きや信頼感が武器になる領域と言えます。
「成長性・将来性を重視」とある求人はミスマッチの可能性アリ

一方で注意が必要なのが、
「成長性」、「ポテンシャル」、「将来性を重視」といった表現です。
こうした求人は、一見ポジティブで採用に積極的なように見えますが、
多くの場合は“若手を長期的に育てたい”という企業の意図を示しています。
つまり、「これから伸びる人材を求める=経験よりも年齢・吸収力を重視」という構図。
40代以降の転職者にとっては、次のような理由でミスマッチになりやすいのです。
・教育期間を長く取る前提のため、即戦力枠ではない
・そもそもが若手中心の職場文化である
・“将来性”の評価基準が、どうしても若年齢層に偏る
もちろん、業界やポジションによっては例外もありえます。
しかし、こうしたキーワードが頻出する求人は、
「若手の採用枠」と割り切って別の選択肢を探すのが賢明です。
40代以降に求められるのは、ポテンシャル(将来性)などではなく、”即戦力”だと割り切りましょう。
このように、求人票の数行に書かれた言葉には、
企業がどんな人材を欲しているかの“ホンネ”が見え隠れしています。
・「経験重視」「人物重視」=40代でも採用チャンスあり
・「成長性」「将来性」=若手育成枠の可能性が高い
求人票を読む際は、この違いを敏感に感じ取ることが大切です。
次章では、こうした“求人の見極め”を踏まえて、
40代の転職者が実際に「年齢の壁を突破する」ための3つの戦略を紹介します。
40代転職者が“年齢の壁”を突破する3つの戦略
「40代は転職が難しい」とよく言われます。
確かに、20代や30代に比べれば求人数は減りますし、採用のハードルもグンと上がります。
しかし実際には、“年齢の壁”は越えられないものではありません。
多くの40代転職者が内定をつかんでいるのは事実です。
(※正確には、ある程度業種や職種を選り好みしなければ。)
その鍵を握るのが、自分の価値をどう伝えるかという「戦略」になります。
ここでは、私が実際に取り組んで成果を感じた“3つの突破法”を紹介します。
突破法① スキルの棚卸しで「即戦力性」を明確にする

まず最初のステップは、「自分が何を提供できるのか」を明確にすることです。
年齢を重ねるほど、キャリアは複雑多岐に渡ります。
特に自分のように転職を繰り返す人は、それぞれの経験が貴重なものであっても、
キャリアにバラツキが出てくるケースが多いです。
だからこそ、今一度スキルの棚卸しをしておくことが重要です。
自分のどんな点を、「即戦力」として活かせるのか。
具体的には、次の3点を整理してみましょう。
(1)実績(数字や成果)
例:「営業目標を3年連続で120%達成」「新人教育を5名担当」など
(2)スキル(得意分野・専門性)
例:「チームマネジメント」「クレーム対応」「プロジェクト進行管理」など
(3)経験から得た学び
例:「人との信頼関係構築が成果につながることを実感」など
こういったことを紙に書き出すだけでも、自分の市場価値とも言える“武器”が見えてきます。
企業は40代に対して“即戦力性”を期待しています。
その期待に応える準備を整えることが、最初の突破口です。
突破法② 企業目線で“採用メリット”を伝える自己PRを作る

次に重要なのが、自己PRを“企業目線”で組み立てることです。
多くの転職者がやりがちなのは、「自分がこれからどうなりたいか」ばかりを語ること。
いわゆる、”自分語り”というものですね。
しかし企業が知りたいのは、「あなたを採用するとどんなメリットがあるか」です。
以下のように、企業側の目線に立って、自己PRを整理してみましょう。
| NG例(自己中心) | OK例(企業目線) |
| 「新しい環境でスキルを磨きたい」 | 「これまでの経験を活かし、即戦力としてチームの成果に貢献できます」 |
| 「マネジメントを学びたい」 | 「若手育成にも携わり、組織力向上に貢献できると考えています」 |
私もこのような気づきを得てからは、面接でこの点を意識したところ、
面接官の反応が明らかに変わってきました。
自己PRは“自分語り”ではなく“相手への提案”なのです。
自分という、労働市場における”商品”をいかに売り込むか。
この発想に切り替えるだけで、採用担当者の心に響くメッセージになります。
突破法③ 年齢を理由に諦めない転職マインドを持つ

そして最後に大切なのは、年齢を言い訳にしないマインドです。
40代で転職活動をしていると、書類選考の段階で落とされることが多く、
正直、心が何度も折れそうになります。
しかし、そこで「もうダメだ」と諦めてしまうのは、もったいない話です。
実際、40代で成功している人には、共通して以下のような“継続力”があります。
・応募が通らなくても、少しずつ改善を繰り返す
・面接で落ちても、振り返って次に活かす
・周囲の意見に左右されず、自分のペースで続ける
“年齢の壁”というのは案外、自分自身が勝手に作り出している場合も多いです。
転職活動は、自分を見つめ直すプロセスでもあります。
年齢を重ねているからこそ持てる強み――それを信じ、前へ進むこと。
このマインドが、40代の転職成功者に共通する最大の武器です。
次章では、
企業がなぜ年齢制限を設けたがるのか――その“本音”を読み解きながら、
「年齢に縛られない働き方のヒント」を掘り下げていきます。
年齢制限を設ける企業の“本音”とは?
どうして企業は「年齢制限」を設けたがるのでしょうか?
表向きは「年齢に関係なく活躍できる社会」と言われながら、
現実には“35歳の壁”や、“40代不利”という言葉がいまだに残っています。
その理由をひもといていくと、
企業が悪意で年齢制限を設けているわけではないことが見えてきます。
むしろ、その背景には「組織を守るための事情」や「採用リスクを減らす目的」もあるのです。
理由①:育成コスト・適応スピードへの不安

企業が最も気にするのは、採用後の“即戦力性”と“順応スピード”です。
40代以上の採用には、どうしても以下のような懸念が生じます。
・業務のやり方を変えることへの抵抗があるのでは?
・新しいシステムや文化に馴染むまで時間がかかるのでは?
・若手社員との関係性がうまく築けるだろうか?
つまり、年齢そのものよりも「環境適応への不安」が根底にあるわけです。
このため企業は、**“育成に時間をかけられる若手を優先”**する傾向が強いのです。
40代で経験豊富だからといって、それまでの考え方に固執することなく、
新しい業務環境に速やかに馴染む柔軟性をアピールすれば、企業の採用側も安心するでしょう。
理由②:社内の年齢バランス・組織構成の問題

もう一つの大きな要因は、チーム全体の年齢構成です。
たとえば、30代前半の上司の下に40代の部下が入る場合、
企業は「マネジメントがしにくいのでは?」と懸念するのはごく当たり前の感覚でしょう。
このように、年齢制限は“人間関係のバランスを取るための措置”というケースもあります。
実際、若手主体のベンチャー企業などでは、
「40代以上は合わないかもしれない」と考える経営者も少なくありません。
ただしこれは、“年齢=不採用”という意味ではなく、
**“カルチャーフィット(社風の合う人)を重視している”**に過ぎません。
企業の側にも、“既存社員の働きやすさ”を守る責任がある――ということです。
そう考えると、この年齢バランス(「年齢制限」)も一理あると理解できるはずです。
理由③:人件費と採用リスクのバランスを取りたい

最後に、年齢制限が設けられる最も現実的な理由。
それが、人件費のバランスです。
40代・50代ともなれば、どうしても給与レンジが上がります。
企業としては「若手2人分のコストで1人を採用するなら…」と考えてしまうわけです。
また、「採用してもすぐ辞めてしまうのでは?」という定着リスクも懸念材料。
「あと数年で定年」というイメージを持たれると、長期雇用の前提が崩れてしまいます。
こうした現実的な経営判断が、年齢制限という形で表れていることも多いのです。
理解することで“戦い方”が変わる

このように見ていくと、
企業が年齢制限を設けるのは「差別」ではなく「リスク回避」であることがわかります。
だからこそ、40代以降の求職者に求められるのは、
“企業側が抱える懸念をどう払拭するか”を自分の言葉で示すことです。
・「新しい職場のやり方を積極的に学びたい」
・「長期的に組織に貢献できる環境を探しています」
・「これまでの経験を若手育成にも活かせます」
こうした言葉を面接で伝えるだけでも、
“年齢”が壁ではなく“信頼の証”へと変わっていきます。
そもそも、壁などないようなものです。
年齢を言い訳にするか、信頼の証に変えるか。
それを決めるのは、結局自分なんです。
「年齢制限」という言葉に振り回されず、
その裏にある企業の本音を理解し、戦略的に行動する。
それこそが、40代転職者が“壁”を乗り越えるための最終的な鍵です。
まとめ〜 年齢制限は「壁」ではなく、自分の価値を見つめ直すチャンス

求人票に書かれた「年齢制限あり」の一文。
それを見て、応募を諦めてしまう人は少なくありません。
しかし実際には、法律上ほとんどの求人で年齢制限は原則禁止。
たとえ表記があったとしても、それが「応募してはいけない理由」にはなりません。
むしろ、その裏には企業の“採用意図”や“人材への期待”が隠れています。
年齢を重ねた今だからこそ――
あなたの経験、対応力、人間的な信頼感こそが、若手にはない大きな強みです。
大切なのは、「自分はもう遅い」と思い込むことではなく、
「今の自分だからこそ、どんな価値を提供できるか」を明確にすること。
スキルを棚卸しし、企業目線で自分の価値を伝え、
そして年齢にとらわれない前向きな姿勢を持つことが、成功への最短ルートです。
転職市場において、年齢制限という“壁”は確かに存在します。
しかしその壁は、乗り越える力を持った人の前では、ただの目安にすぎません。
年齢ではなく、あなたの「これから」が評価される時代へ。
この記事をここまで読み進めたあなたは、もう理解できていることでしょう。
40代だからと臆することなく、相手(企業)の採用人材に対するニーズをつかみ、
分かりやすく自身の即戦力性をアピールしていきましょう。
当ブログでは、他にも転職に関する役立つ記事を多数掲載しています。
以下のページからその記事群を参考にしていただければと思います😀